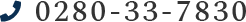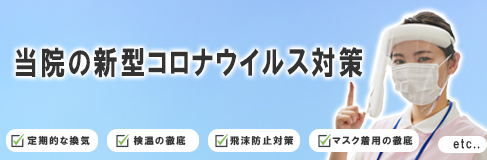保険診療とは、健康保険を適用して行われる治療です。健康保険証をお持ちであれば、どなたでも治療を受けられます。
保険診療時における自己負担の割合は、年齢によって異なりますが、自己負担額が少ないため、治療費を比較的抑えることが可能です。
しかし、厚生労働省が定めるルールにより、治療の内容や使用できる素材が限られています。
そのため、患者さんの症例によっては、保険診療がお悩みの解決に十分ではないケースもございます。
- 自己負担額を抑えた治療ができる
- どの歯科クリニックでも費用がほとんど同じ
- 適用範囲が広く、様々な治療で健康保険を利用できる
- 治療内容や使用できる素材が限られる
- 1回の治療時間が短いケースがある
- 患者さんのお悩みの解決が十分にできるとは限らない
自費診療は保険治療のように様々な制限がなく、患者さんのお悩みの解決に合わせた治療法のご提案が可能です。
天然歯とほとんど変わらない見た目の美しさを持ち、機能性も重視した素材を使用できます。
治療費は全額自己負担となるため、保険診療に比べ高額になるケースもございます。
当クリニックは、患者さんのライフスタイルに合わせ、様々な治療プランのアドバイスも行っておりますので、ご安心ください。
- 天然歯に近い強度や色合いを持つ素材が使える
- メタルフリーで患者さんの体に優しい治療
- お悩みに合わせた治療のご提供が可能
- 治療費が高額になるケースもある
- 歯科クリニックにより、治療費が異なる
- 精密な治療を行うため、治療期間が長期化しやすい
医療費の合計が10万円を超えると、確定申告をすれば控除が受けられます。
確定申告書の受け取りには、いくつかの手段があります。
- 税務署や役所、確定申告相談会場で直接受け取る
- 必要書類のメモと返信用封筒を同封し、税務署へ送付する
- 国税庁の公式サイトや電子システム(e-Tax)を利用し、確定申告書のダウンロードや作成をおこなう
2018年度の確定申告から、領収書の提出が不要になりました。しかし、同時に新たなルールが決められています。
- 領収書ではなく、明細書に記入したものの提出が義務化
- 領収書の原本を確定申告の期限日から5年間保証しなければならない
会社から給与が支払われている給与所得者の場合、源泉徴収票の提出が必要です。提出した書類は返却されませんので、コピーした源泉徴収票を手元に残すようにしましょう。
確定申告は例年、2月16日から3月15日の1か月の間に税務署に申告をおこないます。医療費控除の場合、もし期間内に申告ができなかった場合でも還付申告ができます。還付申告とは、過去5年間を遡って医療費控除の申告ができる方法です。例えば、2019年に還付申告をおこなう場合、2013年から2018年までが医療費控除が有効となる期間です。
控除額を計算する場合は、所得金額200万円がボーダーラインとなり、計算式が異なります。
- 1年間で払った医療費-保険金などで補われる金額-所得金額の5%の合計額が、医療費控除額になります。
- 例:所得金額が180万円で1年で支払った医療費が30万円、保険金の補填額が10万円の場合。30万円-10万円-(180万円×5%)=11万円が医療費控除の対象額として還付申告が可能です。
- 1年間で払った医療費-保険金などで補われる金額-10万円の合計額が、医療費控除額になります。所得金額が200万円以上の場合、所得金額の5%を合計額から引くのではなく、一律で10万円を合計額から引くという違いがあります。
- 例:所得金額が300万円で1年で支払った医療費が50万円、保険金の補填額が15万円の場合。50万円-15万円-10万円=25万円が医療費控除の対象額として還付申告が可能です。